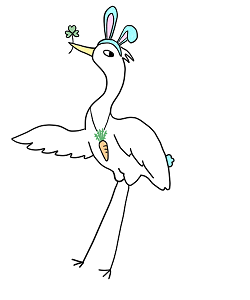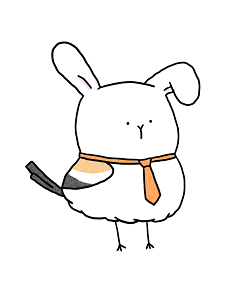Q.ずっと、自分が何のために生きているのかわかりません。他の人のためにもなっていないのに、自分が生きている必要は何なんでしょうか?
A.カエルは何のために生きるとか、生きる必要とかはそもそもないと思っている派です。
意味とか必要性とかは人間が頭の中でつくりあげているものでもあり、カエル的には人間が生きていることで生じる一種の症状のようなものなのだろうと思っています。ただ、誰でも症状が出るわけではなく、真剣に生きようとしていること、物事を深く考えようとすること、そして何らかの苦悩が掛け合わされたときに出るのだろうとカエルは分析しています。
そして、何のためにいきるのか、生きる必要性というものの結論はわりとどうでもよく、そのことに悩み、迷うプロセスに人間らしさが隠れているようにカエルは思うのです。カエルは人間ではないので細かい機微までは理解しきれていませんが、脳が複雑な構造になり、考える余地が多い人間らしさがそこにはあると感じます。
回答:生きかたカエル

★質問を送りたい方はこちら→質問BOX