Q.「いじめ傍観者も加害者と“同罪”」は極論だと思いますか?
また、
「いじめ傍観者を非難する貴方は人を助けられるのか?」
という指摘についてどう思いますか?
A.なるほど…そういった論があるのですね。どんな論も、誰がどういう立場で言っているかで話は変わってくるとウ・サギは思うので、まずそのあたりを整理したいと思いました。
質問への補足から「いじめ傍観者も加害者と“同罪”」「いじめ傍観者を非難する貴方は人を助けられるのか?」はネットで目にした言葉のようなので、そうなると誰がどういう立場で言っているかわからないですね……困りました。ただ、それを目にして揺れ動く質問者さんの心はよく伝わってきたので、そのあたりも踏まえながら、場合分けをしていろいろと考えていきたいと思います。
「いじめ傍観者も加害者と”同罪”」について
①発言者が、いじめられた/いじめられている当事者の場合
これについては全く極論だと思いません。「その通りですごめんなさい」以外にウ・サギは返せる言葉がないです…。
②発言者がいじめられた経験があるわけでなく、ただ一般論として罪について語っている場合
これは極論というよりは、なんか主語の大きいことを勝手に言っているなあ…と、そのスタンスにウ・サギはちょっと呆れてしまう気持ちです。罪は人でなく行為に対して生じるものだと思うので、傍観者、加害者ではなく、いじめ傍観行為、加害行為についての論にするべきだと考えます。
③「いじめ傍観行為も加害行為と”同罪”」についてウ・サギはどう思うか
ウ・サギは基本的に誰しもが罪を犯したことのある&これからも罪を犯しうる存在だと考えているので、そもそも全員が罪人というベースで考えています。だから、誰もが適切に自分の罪を償っていきましょうと思うと同時に、適切な償い方はそれぞれに違うと思っています。、償い方で比較したときには、加害行為の償いは被害者の安全を守るための選択に従うこと(例えば、いるだけで被害者の登校が難しいなら転校するなど)や学び直し、傍観行為の償いは傍観しない自分(安定した人間)になれるように生きていくこと、みたいに異なるとは思うので、罰則の重みが同じ=同罪と定義するなら、同罪ではないという答えになりそうです。ただ、ウ・サギは子どものいじめについての責任は100%大人にあると考えています。
「いじめ傍観者を非難する貴方は人を助けられるのか?」について
ネットでいじめ傍観者へのバッシングが起こった中、バッシングしている人たちへの反論や問いかけとして、「非難するなら、あなたは同じような状況で人を助けられるんですよね?」という話が出てきたということでしょうかね(その認識で回答します)。キリストの「あなたたちの中で 罪を犯したことのない者が この女に、まず石を投げなさい」とかなり近しいものだとウ・サギは受け取っています。
これについては、そもそも何かの属性や行動で一面的に「○○者」と人をくくって、ああだこうだ評価することが(バッシングはもちろん、褒めることも)単純にマナー違反だとウ・サギは思っています。だから「そんな貴方は人を助けられるのか?」という問いかけをするまでもなく、「あなたのしていることはマナー違反ですよ。誰かを非難するのでなく、アイメッセージで、自分の経験や思いから話を始めてください」と諭したい気持ちにウ・サギはなります。
回答が長くなってしまいました。インターネットが発達し、いろんな人と言葉でやり取りのすることのできる時代になりましたが、それが対話ではなく論の合戦にしかなっていないことが多い気がして、どうしたらいいのかなあ……と最近考え込んでいるウ・サギです。
回答:ウ・サギ
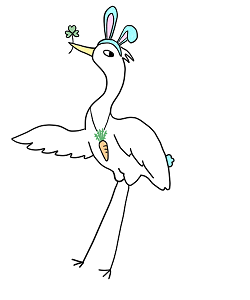
★質問を送りたい方はこちら→質問BOX